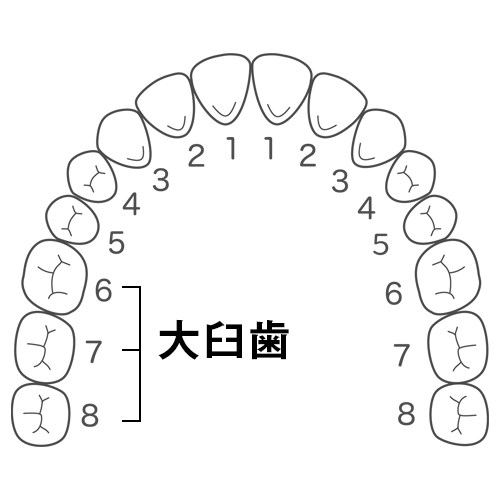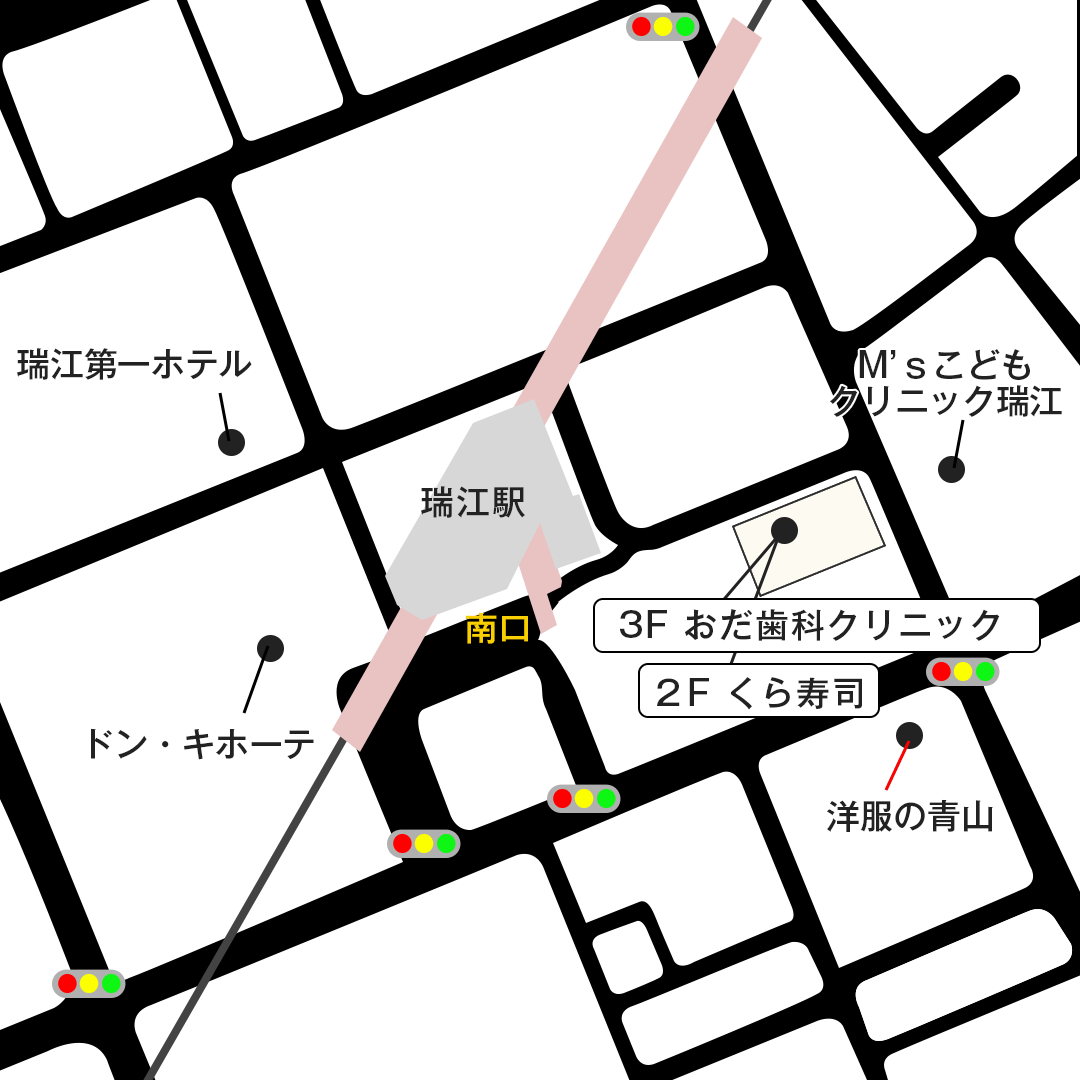歯並びを良くするには? 日常生活で歯並びを良くする方法を解説

歯並びは親から遺伝するものだと勘違いされがちですが、実は日常生活の習慣や癖によって大きく左右されることをご存じでしょうか。
今回は、日常のちょっとした行動や癖を見直すことで歯並びの悪化を防ぐ方法を解説しつつ、矯正治療を検討する際のポイントについてもご紹介します。
目次
■歯並びは日常生活で左右される
◎悪い癖が歯並びを乱す原因になる
歯並びが悪くなる原因のひとつに、日常生活での癖があります。
例えば、頬杖をつく、横向きで寝る、舌で前歯を押すなどの癖があると、歯や顎に持続的な力がかかり、歯の位置が少しずつずれていくことがあります。
また、食事の時に片側ばかりで噛む、噛む回数が少ない、口呼吸が多いといった習慣も、歯列を悪くする原因になります。
◎子供の頃の習慣が将来の歯並びに影響する
歯並びに関するトラブルは、乳歯の時期から始まっていることが少なくありません。
長期間の指しゃぶりや、哺乳瓶での授乳の長期化、舌の位置異常(低位舌)などは、将来的な歯列不正や噛み合わせの問題につながるのです。
特に成長期の子供は骨格が柔らかいため、ちょっとした癖でも歯の動きや骨の発達に影響することがあります。
■歯並びを良くするために意識したい習慣
◎正しい姿勢を保つ
歯並びを良くするためには、身体全体のバランスが重要です。
特に首や背筋をまっすぐに保ち、顎の位置が自然に収まるように姿勢を意識することがポイントです。
スマートフォンやパソコンを見るときに前傾姿勢になりがちですが、顎が前に突き出るような姿勢が続くと噛み合わせがずれてくる原因になります。
◎鼻呼吸を意識する
口呼吸は、口周りの筋肉が使われにくくなり、舌の位置も下がってしまうため、歯列不正を招く大きな要因となります。
歯並びを良く保つためには、舌が上顎に軽く触れるような位置にあり、常に鼻呼吸をしている状態が理想です。
鼻づまりが続く場合や、口呼吸が癖になっている場合は、耳鼻科や歯科での相談をおすすめします。
◎よく噛んで食べる
やわらかい食事ばかりを好むと、噛む力が弱まり、顎の骨や筋肉が十分に発達しません。
歯並びを良くするためには、しっかりと噛んで食べることが大切です。
特に、片側ばかりで噛むのではなく、左右バランスよく噛むよう意識しましょう。
噛む力が育つと、顎が広がり、歯がきれいに並ぶスペースを確保しやすくなります。
◎舌と口周りの筋肉を鍛える
舌の位置や動きは、歯並びに大きく関与しています。
舌が低く前方にある低位舌の状態だと、前歯を押す力が働いて、出っ歯や開咬(かいこう)の原因になります。
舌を上顎に付ける練習や、唇を閉じる筋力を鍛える簡単な体操など、口腔筋機能療法(MFT)の要素を取り入れたトレーニングは、自宅でも取り組むことができます。
■自力での矯正にはリスクがある
◎ネット上の情報には注意が必要
自力で歯並びを治す方法として、ゴムや指で歯を押すといった民間療法的な方法が紹介されていることがあります。
しかし、矯正治療は専門的な知識が必要な治療です。知識もなく歯を動かそうとすると、歯根や歯肉を傷つけるなどのトラブルを起こす可能性があります。
◎気になる場合は矯正相談へ
歯並びが気になる場合は、自己流で無理に整えようとせず、まずは矯正歯科での相談を受けるのが安全な方法です。
近年では、透明なマウスピースで目立たず矯正を行う方法も増えており、患者様のライフスタイルに合わせた選択肢が広がっています。
【毎日の習慣を見直すことが歯並び改善の第一歩】
歯並びは生まれつきだけでなく、日常の癖や生活習慣によって影響されるものです。
良い姿勢を保ち、鼻呼吸を意識し、よく噛んで食べるといった基本的な行動の積み重ねが、歯並びを整える土台となります。
ただし、すでに目立った歯列不正がある場合や噛み合わせに問題がある場合は、自己判断で対応せず、早めに歯科での診断を受けましょう。